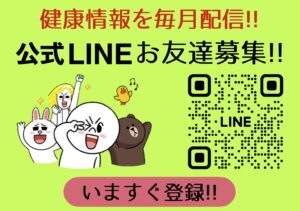こんにちは。吹田江坂女性専用整体Vitaです。
最近、「寝ても疲れが取れない」「前よりも体がだるい」と感じる30代40代女性が増えています。仕事、家庭、子育て、介護…ライフステージの変化が重なる世代だからこそ、心と体の負担は大きくなりがちです。
しかしその疲れ、「年齢のせい」と片づけてしまっていませんか?
実は生活習慣だけでなく、ホルモンバランスや自律神経、さらには病気のサインが隠れていることもあります。
本記事では、疲れが取れない30代女性・40代女性に向けて、原因とチェック方法、改善のヒントを詳しく解説していきます。
目次
1. 疲れが取れない30代・40代女性が増えている理由

女性ホルモンの変化
30代後半から40代にかけては、エストロゲンの分泌が少しずつ減少していきます。いわゆる「プレ更年期」の始まりです。ホルモンバランスが崩れると、疲労感や気分の落ち込み、頭痛や不眠といった症状が出やすくなります。
仕事・家庭・子育てによるストレス
30代・40代の女性は、キャリアの責任も増し、同時に家庭や子育て、親の介護なども重なりやすい時期です。多忙さからくるストレスが自律神経を乱し、体が常に緊張状態になることで疲労が抜けにくくなります。
睡眠の質の低下
スマホやパソコンを使う時間が長いと、ブルーライトの影響で睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑えられ、眠りが浅くなります。結果的に、朝起きても疲れが残りやすくなります。
2. 疲れが取れない30代・40代女性「10のチェック項目」
「疲れが取れない30代から40代女性」にとても多い、生活習慣上の自覚症状を10のチェックリストにしました。
以下の項目に3つ以上当てはまる場合は、体からのSOSサインかもしれません。
- 朝起きても体が重い
- 日中に強い眠気を感じる
- 以前より集中力が続かない
- 肌荒れや髪のパサつきが気になる
- 生理周期が乱れてきた
- 動悸や息切れを感じることがある
- 気分が落ち込みやすい
- 便秘や下痢を繰り返す
- 肩こりや頭痛が慢性的にある
- 体重の増減が激しい
あなたはいくつ当てはまりますか?これらは放置せず、原因を見つけ対処していくことが大切です。
それでは今度は、「疲れが取れない」原因について詳しく探っていきましょう。
3. 疲れが取れない30代・40代女性に考えられる主な原因
栄養不足(鉄分・ビタミンB群・タンパク質)
女性は月経によって鉄分を失いやすく、30代40代になると「隠れ貧血(鉄欠乏性貧血)」の人が増えます。
鉄は酸素を体中に運ぶ役割があるため、不足すると細胞に酸素が行き届かず「体が重い」「息切れする」といった症状が出やすくなります。
さらに、鉄をエネルギーに変換するためにはビタミンB群やタンパク質も必要です。忙しい女性ほど食事が簡単になりやすく、栄養不足が疲労の蓄積につながります。

自律神経の乱れ(ストレスやスマホの長時間使用)
仕事・家事・子育てなどで常に気を張っていると、自律神経のバランスが乱れます。
本来は昼に交感神経、夜に副交感神経が優位になるのが理想ですが、ストレスが続くと交感神経が過剰に働き、体がずっと「緊張モード」のままになります。
その結果、眠っても深く休めず「疲れが取れない30代女性」「疲れが取れない40代女性」が増えているのです。特にスマホのブルーライトは交感神経を刺激するため、寝る前の長時間使用は要注意です。
ホルモンバランスの変化(エストロゲン低下、PMS、更年期)
30代後半から40代にかけては、女性ホルモンのひとつ「エストロゲン」が徐々に減少します。エストロゲンは自律神経や骨、血管、脳の働きを支える重要なホルモン。
そのため、分泌が減ると「のぼせ」「動悸」「イライラ」「疲れやすさ」といった更年期に似た症状が現れることがあります。また、ホルモンバランスの乱れは睡眠の質にも影響するため、疲労が慢性化しやすいのです。
隠れ貧血や甲状腺の不調
健康診断で「貧血なし」と言われても、実際には鉄を蓄える力(フェリチン)が不足しているケースがあります。これを「隠れ貧血」と呼び、強い倦怠感や集中力の低下を引き起こします。
また、甲状腺の働きが低下すると、代謝が落ちて「強い疲労感」「むくみ」「体重増加」といった症状が現れます。
逆に甲状腺機能が過剰になると、動悸・発汗・体重減少などを伴い、いずれも「原因不明の疲れ」として見過ごされがちです。
体液循環の低下(リンパ液・脳脊髄液・間質液)
疲労感は血流だけでなく、リンパや脳脊髄液などの流れが滞ることでも悪化します。リンパの流れが悪いと老廃物が排出されにくくなり、むくみやだるさを招きます。
また、脳脊髄液の循環が乱れると、脳の疲労物質が溜まりやすく、頭が重い・集中できないと感じやすくなります。デスクワーク中心の生活や運動不足は、この循環不良を起こす大きな要因です。

姿勢の悪化(猫背・巻き肩・スマホ首)
長時間のデスクワークやスマホ使用により、猫背や巻き肩、首が前に出る「スマホ首」になりやすくなります。
姿勢が悪いと筋肉が常に緊張して血流が滞り、肩こりや頭痛を引き起こします。また、胸郭が圧迫され呼吸が浅くなり、酸素不足で疲れやすい体質につながるのです。
腸機能の低下(腸下垂、腸内細菌の乱れ)
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、心身の健康に深く関わっています。腸の位置が下がる「腸下垂・腸落下」や、腸内細菌のバランスの乱れは、便秘や下痢だけでなく、栄養の吸収不良や免疫力の低下を招きます。
腸が不調だと必須栄養素をうまく取り込めず、疲労回復が遅れる原因となるのです。さらに腸はセロトニン(幸せホルモン)の多くを生み出しているため、腸の不調は気分の落ち込みにも直結します。
4. 疲れを溜めないための生活習慣の見直し

質の良い睡眠をとる
メリット:深い睡眠は成長ホルモンを分泌し、体の修復や疲労回復を助けます。自律神経が整い、翌朝の目覚めもスッキリします。
工夫:寝る1時間前にはスマホやパソコンを手放し、照明を暖色系に切り替えましょう。また、眠る前に軽いストレッチや深呼吸を行うと副交感神経が優位になり、眠りに入りやすくなります。

バランスの良い食事を意識する
メリット:栄養素をしっかり補給することでエネルギー代謝がスムーズになり、日中の集中力や持久力が高まります。鉄分を十分に摂ると貧血予防になり、疲れやすさが改善されます。
工夫:毎食「主食・主菜・副菜」を意識するだけでも栄養バランスは整います。特に朝食では卵や納豆、ヨーグルトを取り入れると一日を元気にスタートできます。外食やコンビニ食ではサラダチキンやおにぎり+野菜スープなど、タンパク質+ビタミンを組み合わせるのがおすすめです。

軽い運動やストレッチ・腸もみマッサージ
メリット:血流を促進して老廃物の排出を助けるため、疲労物質が溜まりにくくなります。腸もみを取り入れると便通改善や腸内環境の向上につながり、免疫力アップや気分改善も期待できます。
工夫:激しい運動でなくてもOK。朝起きたら伸びをする、昼休みに5分歩く、寝る前に腹部を「のの字」にやさしくマッサージするなど、小さな習慣で十分効果が出ます。続けることが大切です。
特にセルフで行う「腸もみマッサージ」は慢性的な疲れを取るためのセルフケアとしてとても有効です。以下のリンクから、超もみマッサージの具体的な方法について解説しています。興味がある方はチェックしてみて下さい。

マインドフルネス(瞑想法)や深呼吸
メリット:副交感神経を刺激し、脳と体をリラックスさせます。ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑えられ、心が安定する効果も。数分でも取り入れると気分が切り替わり、疲労感が和らぎます。
工夫:朝の通勤前や夜寝る前に、1分だけでも呼吸に意識を向ける時間を作りましょう。アプリを使ったガイド付き瞑想もおすすめです。初心者は「吸う4秒、吐く6秒」を意識するだけでも十分。

正しい姿勢を意識する
メリット:姿勢が整うと筋肉や関節への負担が減り、血流や呼吸もスムーズになります。酸素が全身に行き渡ることで集中力や回復力が高まり、慢性的な肩こり・頭痛の改善にもつながります。
工夫:デスクワーク中は椅子に深く座り、骨盤を立てるように意識しましょう。スマホを見るときは目の高さに持ち上げるのがポイント。仕事中に1時間に1回は立ち上がり、肩回しや首のストレッチを取り入れると効果的です。

整体院での定期メンテナンス
メリット:専門家の手で筋肉や骨格の歪みを整えることで、血流やリンパの流れが改善し、疲労回復がスムーズになります。セルフケアだけでは難しい「体のクセ」の改善にもつながります。
工夫:整体は症状が出てから行くのではなく、月1回の定期メンテナンスとして通うのがおすすめです。自分の体の状態を知ることで、日常生活の改善点も分かりやすくなります。
5. 病気が隠れているサインに注意
疲れが長引く場合、病気が関係していることもあります。
・慢性的な疲労感+動悸・息切れ → 貧血や心疾患の可能性
・だるさ+体重増加/減少 → 甲状腺機能異常の可能性
・強い疲労+気分の落ち込み → うつ病や自律神経失調症の可能性
こうした症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
6. まとめ:疲れが取れないときは「心と体の両面ケア」を
30代・40代女性は、ホルモンの変化や生活環境の多忙さから疲れが溜まりやすい時期です。「年齢だから仕方ない」と思わず、まずは食事・睡眠・姿勢・運動・整体院で体のコンディションを整え、必要に応じて医療機関で検査を受けましょう。
疲れが取れないというのは、体からの大切なサイン。心と体を整えることで、また元気な日常を取り戻すことができます。